どうも、競馬ナビゲーターの北澤です。
突然ですがあなたは競馬予想における
”ラップ理論”についてどんなイメージを持っていますか?
一時期YouTubeを賑わせた人にラップの教材を扱った方がいたので
「何かうさんくさい」と思う人もいるかもしれません(笑)
そうでなくても”前傾戦”や”後傾戦”といった言葉が紛らわしく
なんとなく「とっつきにくい」と感じている方もいるでしょう。
しかしこの記事を読んで下さっているということは
多かれ少なかれラップに興味がある人だと思います。
そこで今日は競馬予想におけるラップ理論について
基礎的な知識と内容をお伝えてしていきますね!

ラップとは
競馬のレースにおいて「勝ちタイム」は常に注目を浴びます。
”1600mを1:30:9で走った”とか
”2000mを1:56:8で走るなんて凄い”などなど。
誰もが決着時計は注目しますし、
なんとなく速い遅いの目安はイメージしやすいですよね。
しかし、実際のところレースでは
1ハロン(200m)ごとのタイムも計測されていて
このハロン毎のタイムを「ラップタイム」と呼びます。
最小単位のハロンにまで分解することで
レース展開の詳細な分析が可能になりますし、
スパートのポイントも把握できるようになります。
したがって言い換えるのであれば
”レースはラップタイムの連続によって構成されている”
と表現することもできるのです。

ただし、個々の馬のラップタイムは通常知ることができません。
JRAのホームページで掲示されているのはあくまで
レース全体のラップタイムであり、
ラップを計測している地点で先頭だった馬の
ラップタイムをスタートからゴールまで表示しているだけです。
言い換えるなら逃げ馬がスタートからゴールまで終始先頭だったなら
「レースのラップタイム=逃げ馬(勝ち馬)のラップタイム」になるし
逃げ馬が残り400mで交わされたのであれば
スタートから残り400mまでは
「レースのラップタイム=逃げ馬のラップタイム」で、
残り400mからゴールまでの2ハロンは、
「先頭に立った馬が刻んだラップ=レースラップ」となります。
ラップタイムで見えるもの
ラップタイムを分析することでわかるのは
「そのレースで一体何が問われたか」
「上位入線した馬は共通してどのような能力を満たしていたか」
といった事実です。
たとえばスタートから残り600mまではスローで
残り600mから極端にラップが速くなっているのなら
上がり3F(600m)でどれだけの脚を使えるかが重要だったレース。
反対にスタートから速いペースでレースが進み
最後の600mは失速しているラップだったのであれば
バテずにいい脚を長く使う持久力が問われるレースだった
という分析ができます。

このように過去のレースのラップタイムを分析することで
その馬の適性がわかります。
そして今回馬券を買おうとしているレースでは
どんな適性が要求されるのか?ということを
メンバー分析や展開予測することであたりをつけ、
要求されそうな特徴や適性に合致する馬を買う。
こうしたペース・ラップ判断から買うべき馬を見つけられるのが
ラップ理論のいいところなのです。
ラップタイムの基準
では次に、ラップタイムの速い遅いの基準を紹介します。
基本的に1F(ハロン)ごとのラップタイムはほとんどが
13秒~11秒の中で推移します。
もちろん距離や馬場状態によって判断基準は変わってきますが
およそ以下のように分ける事ができます。
※僕の主観も入っていますので参考程度に。
13.0~ 遅い
12.0~12.9 普通
11.5~11.9 速い
11.0~11.4 かなり速い
~10.9 超速
一般的には上がり3Fが33秒台なら速いと言われますが、
もし上がり33.9秒だったとすれば1F平均が11.3秒です。
この事実からも上記目安の中で「11.0~11.4=かなり速い」
と区分されているのは妥当だとわかるかと思います。

また当然のことながら短距離戦であればスタートから
1F11秒台が続きやすいですし、
逆に長距離戦であればラスト3Fに入るまで
11秒台に突入しないというケースもあります。
そのため芝の中・長距離戦では1F11秒台に入ったタイミングが
スパート地点と見なされることが多く、
このタイミングが早ければ早いほど、
スタミナが問われる持久力勝負のレースだったと
判断されることが多いです。
タイムによる区分
先ほども少し触れましたがラップ構成によって
レースのタイプを分けることができ、
一般的に3つにわけることができます。
①前傾戦→前半3Fの方が後半3Fより速い
②後傾戦→後半3Fの方が前半3Fより速い
③一貫型(トータル型)→前後半のラップ差が少ない
③については予想家によって呼び方が変わりますが、
僕はトータルラップ型とか一貫ペースと呼ぶことが多いです。

主に短距離戦では前傾ラップになりやすく
中・長距離戦では後傾ラップになりやすいです。
だからこそ、中・長距離戦で前傾ラップになると
速いペースにきつくなった先行馬がバテて、
後方で脚を溜めていた馬が差し切る!
というレースも出てきやすくなります。
キャラクターを見抜く
今話してきたことから、
前傾戦に強い=最後までバテないことが要求されるスタミナ戦に強い
後傾戦に強い=最後に速い脚を使う(速い上がりを使える)能力がある
と考えることができます。
それと同時に「トータル型のレースに強い=いい脚を長く使える能力がある」
と評価することもできますね。
またアーモンドアイのように速い上がりを使える馬を瞬発型
反対にキセキのように極端に速い上がりは使えないけど
速いペースで行っても最後までバテない強みがある馬を持続型
と言ったりもします。

レースや競馬場毎に求められるラップの適性は違ってきますので
まずはこのあたりのイメージを掴んで、
レース毎に適した馬を選べるようにしましょう。
まとめ
ラップタイムの分析は個々の馬の特徴分析や
レースで求められる適性の判断に役立ちます。
これを続けていくことで、
”スローペース濃厚で上がり勝負になりそうな時に持続型を買うべきではない”
といった意味が理解できるようになると思いますし、
まずは馬を「瞬発型」「持続型」の
どちらかに分けることの有益性にも
気づくことができると思います。
ぜひ本日の内容を基に、ラップの楽しさを見つけてくださいね(^_-)-☆
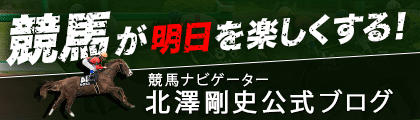
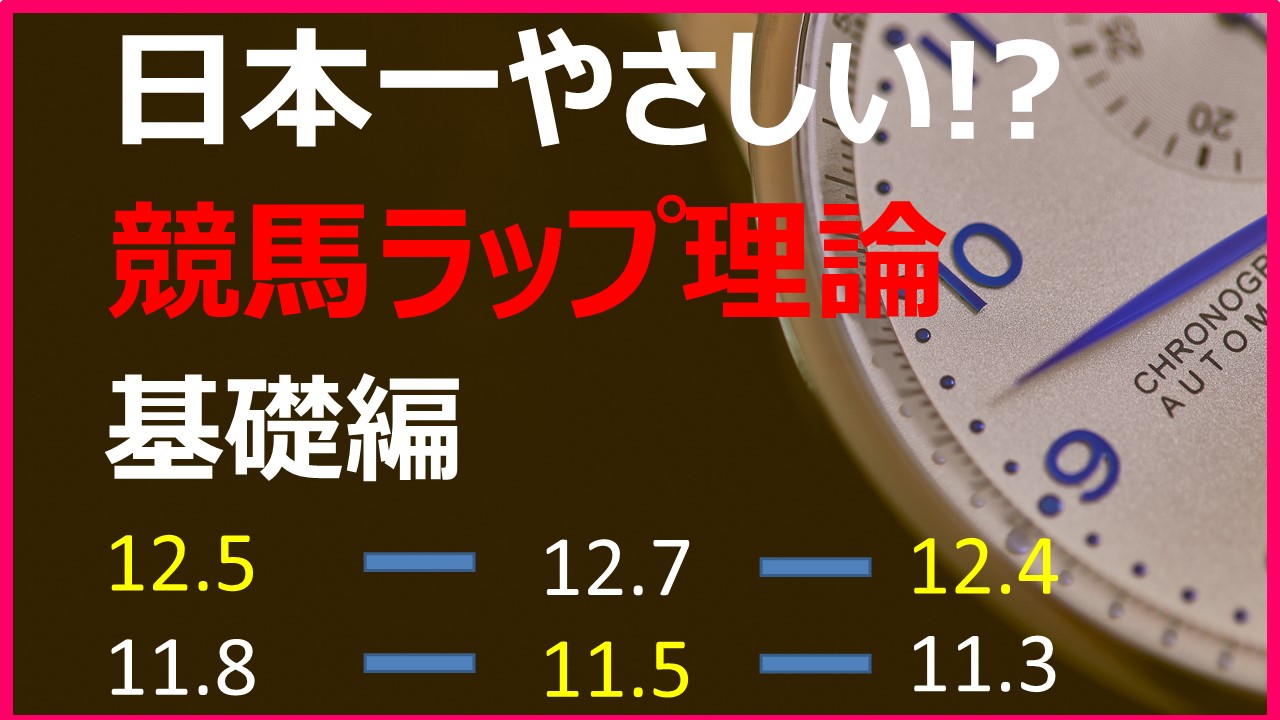
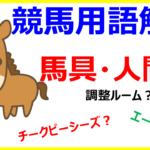

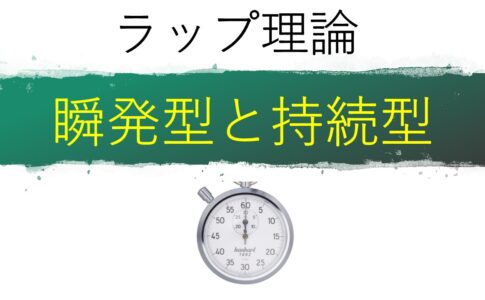





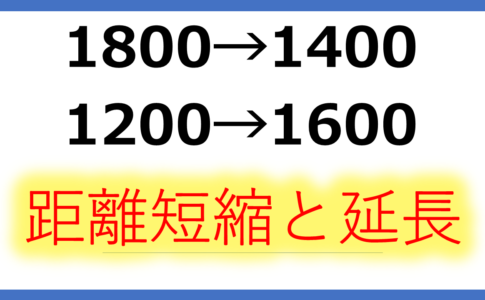

コメントを残す